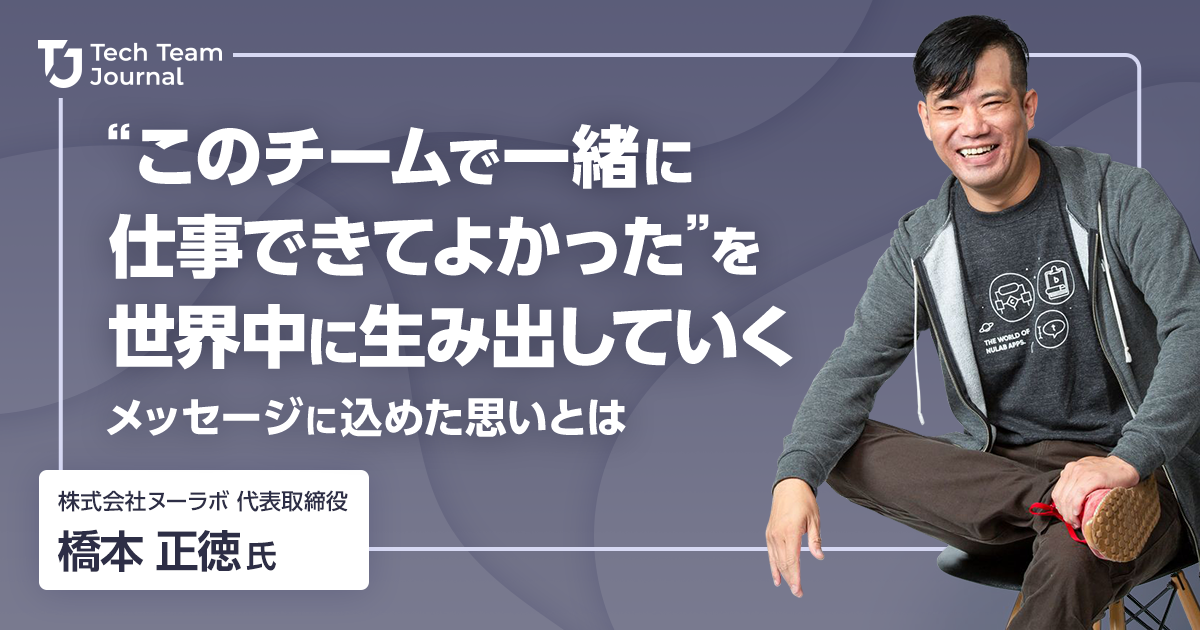今回は、福岡県を拠点に、日本国内に東京、京都、そして、海外にはアメリカ・ニューヨーク、オランダ・アムステルダム、シンガポール・チャンギの3拠点、計6つの拠点を持ちながら、今では勤務地の制約がなくなった企業「株式会社ヌーラボ」に取材をしました。
“このチームで一緒に仕事できてよかった”を世界中に生み出していく――企業のブランドメッセージに込めた想いと、リモートワークシフトに対しての取り組みについて、代表取締役 橋本正徳氏に聞きました。

目次
コロナ禍で変わったこと・変わらなかったこと
――ヌーラボは、コロナ禍以前から複数拠点での企業展開を行い、また、プロダクト自体も国内外問わず、ユーザーのボーダレス化に積極的に取り組んでいた印象があります。その背景から、2020年のコロナ禍になって、企業の活動、働き方、また、リモートワークに向けて何か変わったこと、また、変わらなかったことはありますか?
テレワークへのシフト、テレワーク時におけるコミュニケーション活性化への取り組み
橋本正徳氏(以下、「橋本」):ヌーラボとしては、コロナ禍以前より、(拠点以外での)週1回までのリモートワーク・テレワーク規程を策定していました。ただ、それまでは各拠点のオフィススペースが、いわゆる「働く場所」となっていました。
そして、2020年初頭からのコロナ禍を受け、同年2月中旬からは週1回の制限をなくしてのテレワーク推奨、同年8月5日には、テレワークを継続することに加えて、出社を前提としないワークスタイルへのシフト変更を発表しています。福利厚生については、従来から用意されていた語学学習補助やカンファレンス手当、書籍購入・PC購入手当に加えて、月1万5,000円のテレワーク手当を支給しています。また、勤務地条件が撤廃され、居住地に関係なく働けるようになりました。
結果として、たとえば、2021年12月現在、日本国内の従業員の居住地は、拠点外として、北海道(札幌)、滋賀、愛知、岡山、長崎、大分など、幅広い地域に広がっています。
もともと、自社で開発・運用している「Backlog」「Cacoo」「Typetalk」「Nulab Pass」の各サービスは複数拠点での開発が前提だったため、従業員間でのワークフローの大枠はそのままに、リモートワーク・テレワークに合わせた形へ最適化を進めています。
メタバースの盛り上がり前からVRへ着目
橋本:たとえば、Facebookの社名変更まで含めたメタバース強化をはじめ、今、まさに世界中で盛り上がりを見せるメタバースにいち早く着目し、2021年3月25日には、社員同士のコミュニケーションが促進されることを期待して、全従業員にOculus Quest 2を支給する取り組みも行っています。こちらはまだ模索中ではありますが、テレワーク環境下において、それぞれが直接会っているかのような感覚で雑談を行えるなど、成果にすぐつながるものではなく、企業として、チームとしてのコミュニケーション、一体感の強化を目指したものです。
ブランドメッセージ「“このチームで一緒に仕事できてよかった”を世界中に生み出していく」に込めた想い
――今、伺っただけでも、企業としてのチームに対する強い考えを感じます。また、それを言語化されていると思われるブランドメッセージ「“このチームで一緒に仕事できてよかった”を世界中に生み出していく」を2021年6月に発表されていますね。
橋本:ヌーラボは2004年創業以来、「コラボレーション」をキーワードにした企業活動を行ってきました。これは、ユーザーの皆様に提供する価値の根幹でもあり、「Backlog」「Cacoo」「Typetalk」といったプロダクトのコンセプトにも大きく影響を与えています。
しかし、これは提供する価値にだけ使っているわけではなく、ヌーラボ内にも共通価値観として持っているもので、「楽しく仕事ができる人、チームを増やしたい」という想いでサービス開発や提供を続けています。
そして、2021年6月、世の中がコロナ禍、また、リモートワークにより、物理的な対面が難しくなったからこそ、改めて言語化したブランドメッセージが「“このチームで一緒に仕事できてよかった”を世界中に生み出していく」になります。
コミュニケーションの先にある、開発力、エンジニアチームとしての組織力
――リアル・オンラインに関わらず、コラボレーション、コミュニケーションを重視するヌーラボの姿勢の一端を知ることができました。続いて、エンジニアにフォーカスして話を進めさせてください。
エンジニアの評価は定量評価ではなく、定性評価を行う
――まず、現在の各プロダクトのエンジニアチーム(体制)、構成について教えていただけますか。
橋本:Backlogに30名ほど、Cacoo・Typetalk・Nulab Passに10名ほどのエンジニアが携わっています。また、所属拠点は福岡本社に50名、東京事務所に20名、京都事務所に10名程度です。
――それぞれのプロダクトにおけるエンジニアの評価、また、開発や日常的な業務における特徴はありますか? たとえば、リモートワークでの変化があれば教えてください。
橋本:エンジニアに限らずではありますが、ヌーラボの評価は定量的なものではなく、定性的なものが多いです。ですから、数値化しやすいリリース回数やコード量だけで評価は決まりません。
まず、評価に関して定義をしっかりとするために、5年ほど前から行動規範の改訂に取り組みました。そして、2年前の2019年、現在のヌーラボの行動規範「Nuice Ways」(Ver 2.0)が誕生しています。

橋本:また、行動規範改訂の取り組みとほぼ同時期に、評価制度を年功序列や熱意といった旧来型のものから、グレード制へ大きく変えました。
グレードは全部で7段階あります。1がスタートで、上がっていくにつれて求められる能力が異なります。グレードが上がるに伴って自分が関わっている業務に加えて、他のメンバーをサポートできることなど、他者への影響度がどれだけ高い業務を行っているかといった分類を行っています。
このグレード制の導入は5年前、行動規範の改訂と同時期から導入しました。そのとき、初めて人事専任の人材を採用した背景があります。
導入してからの効果としては、一人ひとりの評価が明確になったメリットと、逆に結果よりグレードへの意識に寄ってしまうケースがあったというデメリットと両方ありますね。
グレード制は継続していく予定ですが、グレードの定義や運用方法は定期的に見直しています。
そして、グレードの最終評価の決定は上長(部門長)が行いますが、現在のグレード制は、まず、本人からの上位グレードへのプロモーションとなる自己申告からスタートし、昇格の検討を行うフローになっています。
評価は現在は年1回の実施です。気持ちとしては年2回行いたいのですが、ヌーラボでは1人の評価に1ヵ月ほど時間をかけており、非常にパワーが必要な業務となります。ですから、私に加えて、フロー上の考課決定者以外も評価に関われる仕組みを作っています。評価には、自己申告の内容、また、評価チームの査定があり、その中では、周囲の人間へのヒアリングを行い、その人の仕事ぶりやNuice Ways(行動規範)に沿った行動をしているかなどをを重要視します。
評価で特徴的なこととしては、部署を横断して構成された、評価に関わってもらうチームのメンバーが入れ替わることです。入れ替わりには私の意見(指名)ではなく、そのチーム内での推薦を取り入れている点が、状況や会社の成長に合わせた評価につながっていると感じます。
グレード制導入前からも、360度フィードバックを行うなどして、私個人の評価だけではない基準を準備していたのですが、グレード制になったことで、より明確に、また誰もが共通の評価として捉えられるようになっています。
――その他、エンジニアの働き方で変わった部分はありますか? たとえば、育成や、そのための技術情報収集、また、外部へのアウトプット(カンファレンス登壇など)はどうなりましたか?
橋本:先ほど少しお話ししたとおり、もともと多拠点での開発・運用、また、早くからリモートワークへシフトしたこともあって、日常的な業務、とくに開発に関しては大きくは変わっていないです。
もともと多拠点での開発・運用を行っていたため、日常的なコミュニケーションは、オンラインで行われており、その点でも物理的な出社がなくなった完全リモートワークでも、社員間のコミュニケーションは変わらないですね。
情報収集や外部へのアウトプットも、オンラインという形にはなったものの、大きくは変わっていないと思います。情報収集はインターネットを通じて、また、外部へのアウトプットはブログを使った個人の情報発信、今ではあたりまえとなったオンラインカンファレンスへの参加、また、社内での勉強会開催といったものです。
経営者の視点でいうと、裁量労働制のため、個々人が自分たちのパフォーマンスに合わせて業務を行い、非常に効率的に、そして、社員自身が(自分で判断して)最もパフォーマンスを高められる時間帯で働く意識を強めてくれたことが、副次的な効果として見られています。今後もリモートワークを推奨した働き方で進める予定です。
また、これまで育児などの理由で働くことを諦めていた人間にとっても、日常的に働きやすくなったことは、コロナ禍で生まれたリモートワークの、良かった点の1つではないでしょうか。
ただ、たとえば、エンジニアであれば開発や運用以外の部分、具体的にはミーティングだったり、従業員のケアが変わりました。
ミーティングに関してはこれまで、週に1回行っていた顔合わせのミーティングを、1日1回に増やし、また、Zoomなど必ず顔を合わせる状態にしたチームもあります。各自が自分たちのペースで働きやすくなったため、チームとしての一体感を組織側で生み出す仕組みです。
従業員のケアに関しては、エンジニアに限らず、コロナ禍で立場や環境によって日常的な人と人との会話、コミュニケーションの減少が起こるケースが出てきたため、いわゆる「テレワークうつ」予防への取り組みなどを行っています。簡単にできるところでは、緊急連絡先の共有であったり、前述のVRなどを活用した雑談環境の整備です。
また、2021年10月には従業員向けにオンラインでのメンタルヘルスセミナーを開催しました。このセミナーでは、「しなやかな心で生きるヒント」と題し、テレワークで起こりがちなとくに気をつけるべきストレスの認識や、メンタルを健康に保つための生活習慣(睡眠・食事・運動)に関する内容、今すぐできるストレッチの実践といったことを行いました。
とは言え、このまま完全にリモートワークになって、誰も顔を合わせなくなることを望んでいるわけではありません。そこで、最近であればVRを含めたメタバース、あるいは、物理的なオフィスの活用として、対面での会合、インターネット的に言えば、オフ会を明示的に開催する、ということが、コロナ禍が落ち着いた先にある目標です。
コロナ禍後の採用――勤務地条件撤廃が生み出す効果と期待
――エンジニアチームの評価、そして、日常的なワークフローやチームづくりなどについて、ヌーラボとして変わらない部分、また、コロナ禍を意識したものについて伺えました。
今後のチーム作りという観点で、採用についてはいかがですか?
橋本:採用に関しては結論から言えば「大きな変化はない」ですね。その最大の理由が6つの拠点があることで、各地で採用しながらも、採用後はリモートワークでの開発・運用、また、他部署とのコミュニケーションが多いからです。
採用面接、手順は、応募、1次面接通過者は課題を受けてもらいます。この課題は、応募者1人で考えて答えてもらうものではなく、課題そのものをリファクタリングしたり、ヌーラボ社員とともにペアプログラミングをしてもらうプロセスを用意しています。
採用した社員には一緒のチームで働いてもらうからこそ、採用試験の段階から、応募者・ヌーラボ双方で双方を少しでも知ることができるようにしたもので、コロナ禍以前から行っています。
その中で、唯一の変化は勤務地条件の撤廃です。「ヌーラボに入りたかったけど、勤務地が合わず……」というネガティブな断念理由がなくなりました。これについては、この先さらに効果が出て、幅広い人材が採用できるのではないかと期待しています。
期待する人材としては、とにかく新しいものに対してポジティブであること、とくにエンジニアであれば、新しい技術、新しい仕組みをまず触って体験する意識を持っていてもらいたいですね。
今であれば、メタバースやNFTなど、バズワードになっているものでさえも、斜に構えずに、「お、楽しそう」と素直に楽しめる心構えを持っている人材を求めています。
ヌーラボが大切にするオンボーディング施策、継続的なチーム強化への取り組み
橋本:採用後の社員研修、オンボーディング施策および日常的なコミュニケーション施策はコロナ禍を経て、ブランドメッセージを実現できる企業に近づけるよう日々アップデートしています。これは、他社と比較してもユニークかつ最善の取り組みではないかと自負しています。
現在のオンボーディング施策では、入社直後に行う会社説明会とともに、新入社員自身の自己紹介に加えて、人事部からのインタビューを実施し、それをオンラインで全社へ共有します。コロナ禍以前であれば、各拠点に集まって対面で会って、人となりを知ることができましたが、今はそれが難しいため、少しでも以前実現できていた部分を埋める取り組みを増やしている最中です。
また、新入社員向けのダイバーシティ研修、広報担当による情報発信に関する説明会、また、ユニークなところでは、経費精算や手当の申請に関しては説明会ではなく、もくもく会(ハンズオン形式での実践)を行うことで、実体験しながら覚えてもらいます。オンラインになって、画面上だけではわかりづらい部分を補足することを目的としています。
これらはエンジニアに特定したものではありませんが、企業に属する、チームとして働くという点で、非常に重要ですし、こうした部分の安心感を担保することで、エンジニアには、各プロダクトの開発・運用に専念できる環境を整備しています。
その他、コミュニケーション施策として、部署に限られない、「Small Talk」と呼ぶ「斜めの関係性(部署横断)」の1on1ミーティングや、「すごろくトーク」と題した、すごろく形式で展開する雑談ワークショップなど、コロナ禍で失われたであろう部分のコミュニケーションを埋める施策を増やしました。
また、2021年に初めて取り組んだコミュニケーション施策として、ヌーラボ社員向けの冊子「Nulab Teambook 2021」の制作を実施し、2021年12月より全社員に配布を進めています。
Nulab Teambook 2021は、2021年8月末時点、日本国内+国外のすべてのチームの情報についてまとめた冊子です。グローバルで50程度のチーム / 130名ほどのヌーラバーについて網羅的に載っていて、チームの情報は「チームが取り組んでいること、チームの写真、メンバーの写真、メンバーからの一言」から構成されています。情報はすべて英語メイン・日本語併記です。

コロナ後に向けて
橋本:コロナ禍を経験したうえで、2021年はスタートからコロナとの付き合い方、そして、働き方を実践した年でした。すでに述べているとおり、私としてはリモートワークへのシフトは、ヌーラボとして適合していますし、合っていると感じています。
開発チームも成長し、プロダクトも問題なく開発、アップデートされているので、もしコロナが収束し、物理的な日常が戻ったとしても、リモートワークをなくす考えはないです。
そして、これは抽象的な表現になりますが、私は、会社とは「仕事を通じて、社員一人ひとりが思い出づくりをしている場所」と捉えています。コロナ前であれば物理的な出社やコミュニケーションだったものが、すべてオンラインに置き換わったとしても、その体験、その感覚の本質は同じです。
ですから、今の状況での経験を積み重ねることで、社員が皆、少しでもたくさんの思い出をヌーラボの中で積み上げてほしいです。開発や運用というのも、思い出の1つとなるからです。
ただ、コロナははやく収束して欲しいというのは切に願います。仕事以外の部分、とくに、仕事と隣り合わせとなるコミュニティの活動や、福岡という街を横串にしたときに、福岡全体で行えるイベントの開催、また、2019年以前に良い盛り上がりを見せていた、福岡外からの福岡への人材流動を再び活性化させられる企画に取り組みたいです。
一例として、2012年から始めている福岡のテクノロジーイベント「明星和楽」は2022年に10周年を迎えます。ぜひ、良い形で10周年を祝うイベントが開催できる状況になっていることを願います。
最後に繰り返しになりますが、ヌーラボのコーポレートブランドメッセージ「“このチームで一緒に仕事できてよかった”を世界中に生み出していく」はこれからも大切にし、この意識を持った社員が一人でも多く増えるような組織づくりを目指していきます。
――ありがとうございました。
(聞き手:株式会社技術評論社 馮富久)