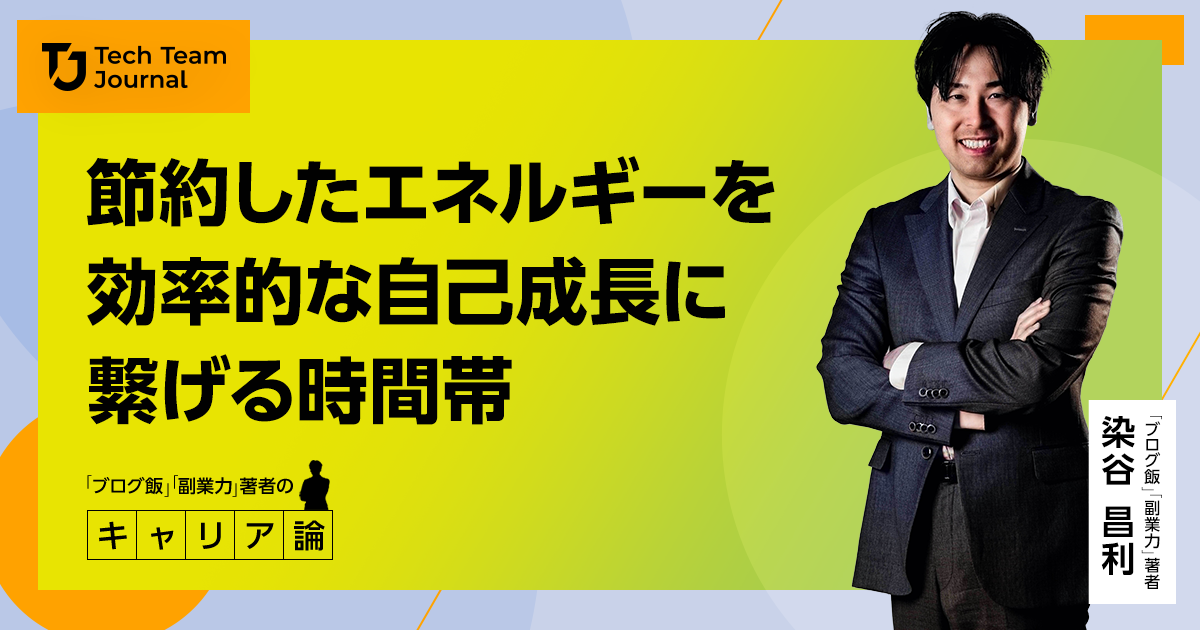ベンチプレスとスクワットがあれば人生におけるほとんどの課題は解決できると思っている染谷です。みなさん、今日も元気に朝から筋トレしてますか。パワー。
筋トレって面白いもんで、意図を持ってトレーニングを続ければ少しずつ持ち上げる重量が増しますし、ちょっとサボると身体が自動的に省エネモードに戻そうとするので(筋肉は代謝が多いので)筋肉量が落ちて思ったように重量を扱えなくなるんですね。
僕の通っていたトレーニングジムではレッグプレス300kgを平気で持ち上げる人間じゃない人たちが群れをなしてるのですが、どれだけ積み上げてきたんだと思いながらハムストリングスを鍛える毎日です。
さて、「自己成長のためのエネルギーマネジメント」の最後でエネルギーを効率的に使う必要性について軽く触れました。300kgを持ち上げるためには、毎日の積み上げはもちろん、いかに効率よくトレーニングをするかによって達成スピードは大きく変わります。
そこで今回の記事では、特に勉強・練習の時間帯について語っていきます。
目次
天才と凡人を分ける要素

ここで一冊、書籍をご紹介します。
ゴリッとしてて良いタイトルですね。マッチョ的な印象を強要する類の書籍ですが、実はこの本には天才と凡人を明確に分ける秘密が各種データや事例とともに解説されています。
Mr.凡人の僕としてはやっぱり天才に憧れるわけですよ。天才の爪の垢を煎じて飲みたいわけです。でも天才ってその辺に落ちてないんですよ。天才の爪の垢を探すより、本を一冊読むだけでその秘密が分かったら安くないですか。
才能は過大評価されている
1992年にイギリスの研究者グループが「生まれつき才能のある人間」を探し出す調査をしています。研究者たちは257人の若者を能力別に、音楽学生になった音楽エリートから6ヶ月ほど楽器演奏をしたが辞めてしまった人まで、5つのグループに分けて調査を実施しました。
その結果、「才能の存在はわからない」ということが分かりました。書籍内では以下のように明記されています。特定の才能の証明ができなかったわけです。
「最高レベルの演奏をする者に音楽での早熟の兆し -我々誰もが存在すると考えている生まれつきの才能の証し- はまったくなかった」
しかしながら、まず一点、生徒が音楽的にどれだけ熟達できるかどうかを予想できる要因が見つかりました。それは「どれほど多く練習するか」ということです。音楽学校に進学するような生徒は、他の生徒に比べて純粋に1日の練習量が多かったという違いが見られたわけです。
「え、それだけなの?」と感じると思いますので、さらに事例を紹介していきます。
モーツァルトやタイガー・ウッズも普通の子どもだった
本書ではモーツァルトやタイガー・ウッズについても言及しています。二人とも誰もが認めるような天才です。天賦の才能とは彼らのためにある言葉と言っても過言ではないでしょう。
モーツァルト
モーツァルトは5歳で作曲し、8歳のときに公式の場でピアニストとバイオリニストとして演奏会をおこない、その後数々の作品を生み出し、21歳であの「ピアノ協奏曲第九番」を完成させ、35歳でこの世を去っています。天才ですね。
モーツァルトの父親レオポルト・モーツァルトは彼自身も有名な作曲家であり演奏家でもありました。父親はモーツァルトが3歳のころから作曲と演奏の面でトレーニングを施したと言われています。音楽家であり、卓越した教師であった父親の指導のもと、モーツァルトは育ったわけです。
なお、モーツァルトの子ども時代の作品の真偽については議論があるそうで、それは父親レオポルトが修正を加えていたという説があります。
モーツァルトが若いころ(特に10代まで)の作品にはモーツァルトの独創的な楽曲が含まれていないとのこと。従来の楽曲を模倣しアレンジすることで、若きモーツァルトのトレーニングとなり、モーツァルトの代表作である「ピアノ協奏曲第九番」やその後の作品に繋がっていったと本書には書かれています。
でも、3歳からトレーニングを始めたモーツァルトが「ピアノ協奏曲第九番」を生み出すまで、18年もの厳しい鍛錬があったことを忘れてはなりません。
タイガー・ウッズ
タイガー・ウッズも同様です。
教育熱心なタイガーの父親アールは、タイガーが生後7ヶ月のときにゴルフクラブを渡しています。そしてタイガーが2歳のときには一緒にゴルフ場でプレーをしています。天才ですね。
タイガーが小学生になるころには地元ではすでに有名で、大学に入るころにはすでに伝説的な存在になっていました。19歳のときには、アメリカ代表チームの一員として国際的な大会で優秀な成績を残しましたが、このころにはすでに17年以上の鍛錬が積まれているわけです。
どうでしょう、モーツァルトやタイガー・ウッズの実績は天賦の才能だけで説明できるのでしょうか。
天才アメフト選手 ジェリー・ライスの事例
僕はそんなにアメフトに詳しいわけではないですが、アメフト好きな人だったら間違いなく知っている超一流のレシーバーです。あれだけ激しいスポーツでありながらも、20年間も第一線で活躍できたのには理由があります。
それは「他のどの選手より、シーズン中もオフシーズンも練習に懸命に努めるから」です。
ライスの偉大な業績を支えた重要なポイントも本書にはまとめられています。ライスを偉大にしたものはいずれもフットボールの試合以外で積み上げた努力でした。
・実戦でうまくなったのではない
ライスが実施にアメフトの「試合」に費やした時間は、アメフトに関することに費やした時間の1%にもならなかった。
・特定の課題を解決するために練習を考案する
本当に必要な課題に注力して訓練を実施し、一般的に必要だと言われる目標、たとえばスピード強化などには力を注がなかった。
・けっしておもしろくない
限界まで走り込んだり、筋肉が言うことをきかなくなるまでウェイトトレーニングを続けることは決しておもしろくない。しかしこうしたことは中核をなす重要な活動である。
トップクラスのプレイヤーは意図を持って、黙々とトレーニングしているわけです。トレーニングに耐えられるだけの身体と心の強さも必要に感じますね。
一流と二流を分けるもの

世間的に見たら天才と思えるゾーンの中にも、さらに一流・二流の区分けがあります。
1990年初頭、非常に優秀な音楽家を輩出することで有名だった西ベルリン音楽学校にて調査がおこなわれました。この学校は全世界から音楽エリートが集ってくるような学校で、入学するだけでも恐ろしい競争の中を勝ち残っているわけです。
この音楽学校に通う学生を、国際的に活躍しそうなバイオリニストグループ(最高)、トップグループではないものの大変上手なバイオリニストグループ(より良い)、入学基準が少し低い大学内の別のバイオリニストグループ(良い)に区分し、データを分析しました。
分析結果は非常に明確でした。
似通っていた項目としては「約8歳でバイオリンを始め、15歳で音楽家になることを決意」「週に音楽関連の活動(個人レッスン・自分一人での練習・クラスでの授業)で1週間の合計時間は約51時間」という点があります。
3つのグループはいずれも朝早く起床し、何時間もバイオリンを練習していました。そして生徒全員が「自分一人で練習すること」が一番重要だと認識しています。
しかし大きな相違点として、その「自分一人での練習する時間の差」がありました。「最高」と「より良い」のグループは1週間平均で24時間、「良い」のグループの練習時間はたった9時間だったのです。
多くの人は認識していても実行に移せません。なぜかというと、一人でおこなう練習はおもしろくないからです。エリートの集まる大学でもそうなんです。みんなでワイワイ練習したほうがそりゃ楽しいですよね。
前回の記事で「孤独に耐えるエネルギー」の話をしましたが、個人で孤独におこなう練習はエネルギーを大きく消耗するわけです。
さらに「最高」と「より良い」グループの場合は、まだ活力のある朝方、あるいは昼食後の早い時間帯に集中して個人練習しています。「良い」グループは日中で最も疲れている午後の遅い時間帯に個人練習をしていることが判明しています。そして上位グループほど体力回復のために、多くの昼寝をしています。
さらにさらにもう一点、「最高」と「より良い」グループの差異は、「18歳までの練習時間」でした。18歳に達するまで「最高」のグループは平均7,410時間練習しており、「より良い」グループは平均5,301時間、「良い」グループは平均3,420時間の練習量でした。
明確に累積の練習量が、そして自分一人での練習量が多い人間のほうが、要は効果的な時間帯に練習している人間が大きな業績を上げていることがデータをして出ています。音楽家やスポーツ選手に限らず、科学者や作家、実業界でも、何十年もの時間を捧げるからこそ輝かしい業績を残せるのです。
達人と素人の違いは、特定の専門分野で一生上達するために「考え抜いた努力」をどれだけおこなったかの違いだと本書では述べられています。
メジャーリーガーのダルビッシュ有選手もこのように呟いてますね。
練習は嘘をつかないって言葉があるけど、頭を使って練習しないと普通に嘘つくよ。
— ダルビッシュ有(Yu Darvish) (@faridyu) June 11, 2010
慣れたらもうトレーニングじゃない

この日本には、霊長類最強ヒト科生命体の室伏広治さんという個体が存在するのですが、僕は昔から大ファンなんですね。
相当昔ですが、「ナンだ!?」という番組でインタビューされた書き起こしがありまして。
「室伏広治が語る独自のトレーニング理論」の中で、室伏さんはこんなことを言っています。
「トレーニングっていうのは、反復すると効果があるっていう風に思うじゃないですか、現に筋肉としては反復したほうが、つくかもしれないですけどでも、運動としてはちょっと厳しいと思うんです。慣れてしまったら、それはもうトレーニングとは言わない。反復しないようにするにはどうしたらいいか、ってことで毎回違うパターンにしてる、自分が読めないようにする、で、慣れてしまったらもうトレーニングだと僕は言わないようにしてるぐらい。慣れたら練習じゃない、出来てるんですから、練習じゃないじゃないですか、だから慣れないほうがいいんですよ」
この書き起こしの中にも載ってるんですが、室伏流握力トレーニングってのがあって、広げた新聞紙を片手でクシャクシャって丸めるトレーニングがあるんですね。(Crumpling paper exercise (improvisational) / 新聞紙トレーニング/室伏広治公式サイト)
自宅のいらない紙を使って試してもらうとわかるのですが、このトレーニング、まったく同じ筋肉を使うことはありえないので、慣れが発生しません。毎回、違う筋肉を使うんです。おそらく室伏さんは「筋肉」という大雑把な括りでは無く「筋繊維」一本一本というディテールにこだわって鍛えている感じがします。
これって運動に限らず、自分の能力値を上げていくための大きなヒントなんじゃないかと思います。
さらにインタビュー内でもう一言。
南原「でも普通考えたら、そのとき怪我したらどうしよう・・・とかなりませんか?なんか慣れないときに」
室伏「慣れたときに怪我するじゃないですか、慣れたころになんでも、怪我とかね」
慣れると油断するんですよね。これも実生活でよくある話です。コンフォートゾーンに居続けていると油断して怪我に繋がります。
さて、ここでもう一冊ご紹介します。
マッスル教の経典です。パワー。
基本的には競技の話が多いのですが、実生活に活かせる内容が各所に散りばめられています。
ちなみに室伏さんは大学の博士課程を終え、2011年4月から中京大学の准教授の職に就いています。そのためか論文的な内容も入っており、単なるアスリートの自伝ではない教典になっています。
私のウォーミングアップは、まずハンマー投に必要な基本的な「動きづくり」と神経や筋肉を呼び覚ますような「身体の動き」から始める。
~中略~
こうしたウォーミングアップを行うことで、身体の土台(ファンダメンタル)が強化され、いわゆる身体の安定性(スタビリティ)が高まり、筋肉などの動きがスムーズになる。身体が正常に機能して動くなかで筋力(ストレングス)強化を加え、使えている筋肉と使えていない筋肉を確認し、どのように稼働させるかというフィジカルトレーニングをおこなっていくのである。
一つひとつていねいに、自分の身体から発せられるシグナルを認識してトレーニングをおこなっていることが読み取れます。すべての行動に必然性があり、何一つとっても惰性でおこなっていません。僕はよく「意識的に」という言葉を使いますが、室伏さんはまさに毎日の行動を意識的におこなっているのでしょう。
高校時代、父からは一流選手のビデオを見なさい。あまりうまくない選手の投げ方は見なくてよいといわれたことがあった。だから下宿では時間が空けば、世界記録保持者のセディフや当時世界歴代2位の記録を持つリトヴィノフのハンマー投のビデオを見ていたものだ。
あるとき大会で同級生のハンマー投の応援をするとき、私だけ一人背を向けていたことがある。「なんだ室伏、お前も応援しろ」と注意され、思わず「親父からいいものを見ろ、悪いものを見てはいけないと言われているので」と答えたら、驚かれた。
ここまで正直に言う必要はないと思いますが、やっぱり時間は限られているので、可能な限り良いもの(良いと思えるもの)に優先的に時間を配分できるようにしなければいけないですよね。ここでも孤独の観点が出てきています。
身体の癒着を取るトレーニングも重要だ。
わかりやすい例が、手の小指だけを曲げようとすると、薬指も曲がってしまうことがある。これが癒着である。これを意識して小指だけ曲げるように集中すれば、癒着を取る訓練となる。
~中略~
癒着を取る訓練をしていると、歳を重ねても身体感覚が鋭敏になり、身体の部位を自由に動かすことができる。私は背骨の一つ一つを動かすこともできる。余分な動きがなくなれば疲労が蓄積しにくくなり、ケガの予防にもなると考えられている。
必然性のある訓練を意識的に行うからこそ、長い期間第一線で戦える身体能力を維持していけるのでしょう。
とにかく超人 室伏広治ができあがるまでの経緯や行動などが盛りだくさんの内容になっています。単なるアスリートの自伝ではない、一流になるために、そして一流を維持していくための考え方を知りたい人はぜひ読んでみてください。
この本に書いてあることを自分の環境に置き換えて、実行し続けられれば周りより一歩抜けた存在になれるかもしれません。
まとめ

天才と超人の話を長々と語って終わってしまった感が強いので、自分の能力を上げるために押さえておきたい大切なポイントをまとめておきます。
- もっとも効率の良い時間帯に、難しい課題に取り組む
- 意図的に、目的を持った練習をおこなう
- 個人練習の時間を多く持つ
- 反復する
- 批判的なフィードバックを常に求める
- 改善すべき点に厳しく焦点を合わせる
- 精神的、肉体的疲労を覚悟する(決しておもしろくない)
最後にタイガー・ウッズが残したと言われる名言を置いておきますね。
No matter how good you get you can always get better and that’s the exciting part.
どれだけ上手くなったとしても、うまくなる余地は常にある。それが面白いところだね。
さて、ここ数回はマッチョ的な話が続いたので、次回は多少テクニックに寄せたタイムマネジメントについてお話します。お楽しみに!
(文:染谷 昌利)